1分でわかる「五木寛之」
多彩な書籍を執筆する「五木寛之」
1932年、福岡県出身の五木寛之。早稲田大学中退後はテレビ局や広告代理店、テレビCMソングの作詞を担当するなど、幅広い活動を行っていました。1965年に小説執筆に取りかかり、1966年に『さらばモスクワ愚連隊』でデビュー。同作が直木三十五賞にノミネートされ注目を集めました。以後、『大河の一滴』(1998)や『親鸞』(2010)、『孤独のすすめ』(2017)などの小説やエッセイ、仏教・浄土真宗の教えをもとに執筆している書籍を数多く発表しています。
実写映画化もされたベストセラー作品の数々
前項で述べたように、幅広いジャンルの執筆を行う五木寛之。『さらばモスクワ愚連隊』や『燃える秋』、『青年は荒野をめざす’99』など、映画化される作品も多数執筆しています。なかでも2001年に公開された『大河の一滴』は、200万部を超える大ロングセラーのエッセイが原作となっており、海外でも絶賛されるほどの大作となっています。
本ランキングにおける「五木寛之の書籍」の定義
本ランキングにおける五木寛之の定義は、彼が手がける作品です。エッセイや共著、随筆の作品にも投票が可能です。ただし、海外の作品を翻訳した文学作品はランキング対象外となります。




















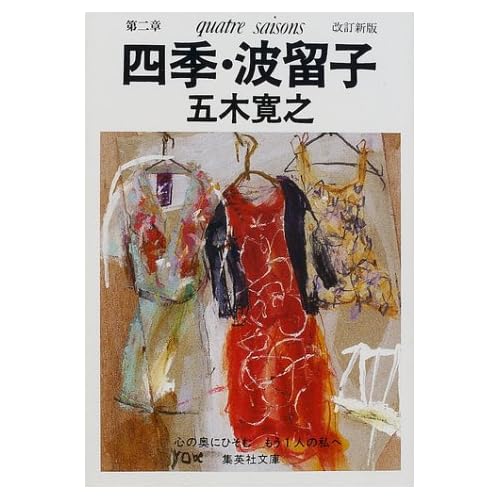



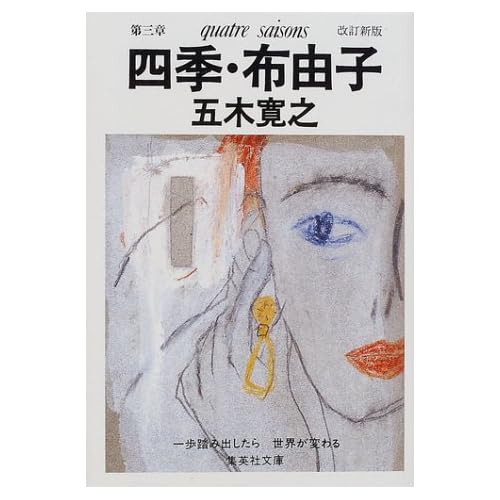
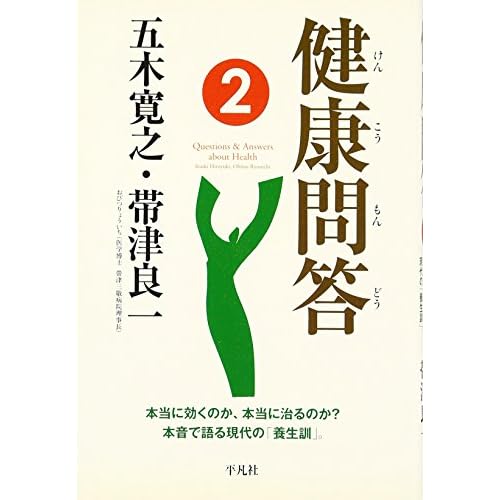
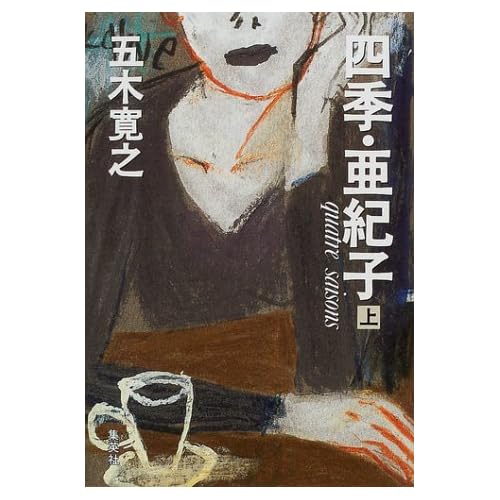
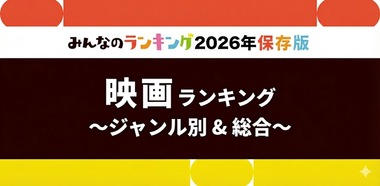
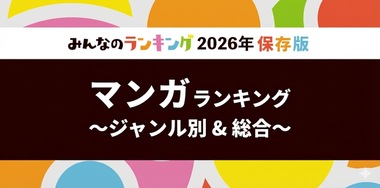











落ち込んだ時に読み直す名作
ブッダや親鸞の教えを随所にちりばめながら、作家自身の体験も踏まえて書かれた人生論。人生で行き詰まりを感じたり日常に疲れた時に読み直したい名作で、生きることの大切さを教えてくれます。本書の中にある生きることそのものが値打ちであるという言葉に救われた人も多いのではないでしょうか。
わたみんさん
1位(100点)の評価
人間は一滴
「大河の一滴」は五木寛之によって書かれた哲学的なエッセイです。哲学的とは言っても、小難しい概念や用語が登場するのではなく、「いまこそ、人生は苦しみと絶望の連続だと、あきらめることからはじめよう」「傷みや苦痛を敵視して闘うのはよそう。ブッダも親鸞も、究極のマイナス思考から出発したのだ」というような、分かりやすく勇気づけられる言葉が散りばめられたエッセイとなっています。所詮は、人間など大河における一粒にすぎない、分かってはいても認めにくい考えを、しっかりと肯定してくれる気がして生きる意欲が湧いてきます。
shutoさん
1位(100点)の評価
それまでに感じたことのない価値観だった
高校在学中から不安障害になってしまい、浪人(ほぼニート状態)の頃に手に取った本です。それまでは「生きること」に精一杯になっていましたが、「死なないこと」によって生きること、そんなことを自分は感じ取りました。
努力家さん
1位(100点)の評価