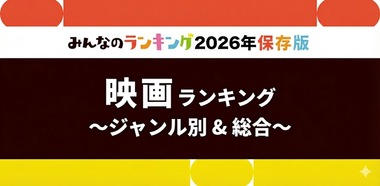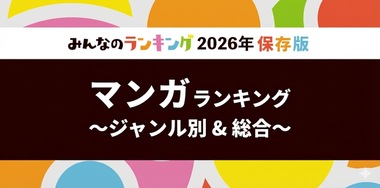1分でわかる「吹奏楽ポップス曲」
コンクールの自由曲に選ばれるポップス曲も多数

銀河鉄道999 / ゴダイゴ
(引用元: Amazon)
木管楽器や金管楽器、打楽器などの楽器がひとつとなってハーモニーを奏でる“吹奏楽”。演奏会やコンクールでは圧巻の演奏ぶりに思わず心打たれる人も少なくありません。王道のクラシックやジャズまでさまざまな楽曲が演奏されますが、コンサートのプログラムやコンクールの自由曲としても人気があるのがポップスです。定番とされる曲には、T-SQUAREの『宝島』(1986年)やゴダイゴの『銀河鉄道999』(1979年)などがあり、親しみやすさに加え、アレンジによって原曲とは違った雰囲気が感じられるのが魅力となっています。