ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位モササウルス
2位ティラノサウルス
後期白亜紀の陸の絶対的王者
まずは何と言っても顎の力。ティラノサウルスを語る上で、このことを忘
れる事はできません。ティラノサウルスの咬合力は、約35000~79000ニュートンにもなったと考えられています。「ニュートン」という単位が分からない人のために、わかりやすい単位に直しましょう。よく聞く重さの単位、「トン」でティラノサウルスの咬合力を計算すると、ざっと3.5~7.9トンになります。いまいちピンと来ていないそこのあなた。同時代の生物の化石からは、よくティラノサウルスの歯型が見つかります。まあ化石に歯型が残ること自体は対して珍しいことではありません。実際、カルノサウルス類の頭骨からは、よく別の生物の歯型が見つかります。しかし、その歯型は削られたような噛み跡ばかり。これに対し、ティラノサウルスがつけたと見られる歯型は削られたような噛み跡ではありません。化石にぽっかり穴が空き、その部分を骨ごと食いちぎられてしまったような噛み跡でした。つまり、ティラノサウルスは相手を骨ごと噛み砕き、そのまま丸呑みにすることができたということです。まだいまいちピンときていないそこのあなた。まあそりゃ親から「魚は骨を抜いてから食べなさい」という教育を受けているはずですからね。ピンとこないというのも分からなくはありません。さて、もっとわかりやすく説明してみましょう。BBCの番組、「肉食恐竜の真実」では、ティラノサウルスの咬合力を知るために、ティラノサウルスの頭骨と全く同じ構造の機械
を作りました。その時の計算では4トンという結果になり、その力で色々なものを噛ませていきました。それを見ていた人たちは呆然とするしかありませんでした。まさか自動車を噛み潰すとは誰も思っていなかったのですから。そう、なんと自動車をたった数噛みで粉々にしてしまったのです。最大でそれの2倍弱の咬合力と考えれば、少しは破壊力が想像できるのではないのでしょうか。少し咬合力の話をしすぎましたかね。それでは次の話を。
顎の力だけでも十分強いですが、ティラノサウルスにはまだまだ強みがたくさんあります。例えばスピード。以前、ティラノサウルスはその巨体故に、まともに走ることができなかったと考えられていました。今でもその考えが定着しているようですが、それは間違っています。最近の研究で、ティラノサウルスの体重が予想より軽かったことが分かっています。そして改めてティラノサウルスのスピードを計算したところ、従来の考えである時速18キロメートルを遥かに超え、時速40キロメートルという脅威のスピードで走ることができたということが分かりました。嗅覚や視覚、聴覚も発達し、昼夜関係なく狩りができた考えられています。また、知能も高かったということが分かっています。今からお見せするのは、恐竜の体に対する脳の大きさを数字で表したものです。
名前 パキリノサウルス 名前 トリケラトプス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
数字 0・4 数字 0・7
名前 アロサウルス 名前ティラノサウルス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
数字 1・8 数字 4・2
これを見れば、違いは一目瞭然。ティラノサウルスの数字が圧倒的に大きいことが分かります。つまり、ティラノサウルスは他の恐竜よりも知能が高かったということです。戦闘に必要なものを全てあわせもった究極の捕食者。 彼らは6500万年の時を経て、我々人類に、ティラノサウルス・レックスと呼ばれています。
後期白亜紀の悪霊
マイプは、後期白亜紀の南アメリカの絶対的支配者でした。同時代に北アメリカを支配していたあの白亜紀覇王と全く互角の戦闘能力を誇り、ありとあらゆる生物を◯す獰猛な捕食者であったと考えられています。マイプの強みは、長さ30cmもの鋭い鉤爪にあります。そもそもマイプの腕自体がかなり長く、そして強靭でした。ですから並の相手ならば鉤爪を見せつけるだけで怯んでしまうでしょう。ただし鉤爪を見せるだけで白亜紀覇王やジュラ紀の覇王、前期白亜紀の南アメリカで猛威を振るっていたあの2大カルカロドントサウルス科が怯むと思いますか?もはやそれで怯んだら彼らはアリ1匹が手の甲に乗るだけでパニックを起こす人と同じくらいビビりになっちゃいますよ…ああ、それは私のことですね。(これマジですからね…)まあ私がビビりなのは置いておいて、マイプは彼らに勝てるのでしょうか。結論。白亜紀覇王以外にはほぼ確実に勝利することができるが、白亜紀覇王だけは場合による。です。あ、ちなみに白亜紀覇王とはティラノサウルスのことです。あるYouTubeで影響を受けましたw、まあとにかく、マイプがティラノサウルスに勝てない理由はたった1つ。顎の力です。白亜紀覇王は他の捕食者と違い肉も骨も問答無用で丸呑みしてたことは皆さんご存知ですね。それに対しマイプは肉をそぎ取るのに適していました。(てゆかほとんどの捕食恐竜の歯の形状がそうです)白亜紀覇王が一撃で相手をあの世に送るのに対し、マイプは何度も相手に噛みついて徐々に体力を消耗させるという戦い方をしていました。森林で彼らが戦えばマイプが勝つでしょう。ティラノサウルスは嗅覚が優れていますが、多分森林では嗅覚でマイプのいる場所を突き止める前にマイプが攻撃をだんだか入れてってしまいます。ただし平原であれば確実にティラノサウルスが勝ちます。障害物が少なけりゃティラノサウルスは真っ向勝負を仕掛けられます。スタミナはティラノサウルスのほうがありますから、マイプがつかれて一瞬のすきにティラノサウルスがマイプの首に食らいつき、マイプはあの世へ行きます。まあ2頭の実力は互角ですが、ティラノサウルスのほうが若干強いと判断したため、今回はティラノサウルスより一つ下位にランクインさせました。
4位ギガノトサウルス
確かに強いは強いけど…
ギガノトサウルスが強いことは認めます。ギガノトサウルスの戦闘能力は確かなものですし、その禍々しい威圧感を放つ強力な牙に噛まれでもしたら、どんな生物でも大量出血は免れないでしょう。しかし、ギガノトサウルスのコメントを見ていると、ゲームでギガノトサウルスが本来の2〜3倍の強さを誇っているせいか、ほーんの少しだけ表現が誇張されている気がします。まずは防御力。ゲームでは防御性能が高いですが、ギガノトサウルスは骨が華奢なため、防御性能はそれほど高くありません。そして大きさ。ゲーム内では25mとかもうわけわからん全長になっていますが、実際の全長は14mとされています。まあ14mでも後期白亜紀の北アメリカに君臨していたティラノサウルスを上回っているので十分大きいですが…と・に・か・く!私が言いたいことは、ギガノトサウルスはゲームよりも弱いということです。(まあ現実でも十分強いけど)
でかすぎる…
アルゼンチノサウルス最大の特徴は、何と言ってもその巨体。
全長40メートル、体重75トンから繰り出されるパワーは、私達には
想像もできないほど凄まじいものでした。私はティラノサウルスとアロサウルスの次にこの恐竜を知りましたが、(なんやかんや言って恐竜に初めて興味持ったの7年前w)この恐竜の詳細を知ったときにはもはや放心状態になりました。全長が40メートルもあるとは思っていなかったからです。アルゼンチノサウルスは、何から何まで規格外です。まず、アルゼンチノサウルスの体格は40億年の生命歴史上、最も巨大な生物でした。なんせ体重は75~100トンに及んだとされているのですから。とりあえずこの恐竜の強みはその圧倒的巨体です。この巨体は、もはや化け物の何者でもありません。しっかーし!ここからが疑問です。アルゼンチノサウルスのその巨体。なぜこれだけの巨体を維持することができたのでしょうか。アルゼンチノサウルスの一日のメシの量は、大体100キロくらいになります。アフリカゾウの一日の飯の量は、大体40〜50キロ。一日に17時間メシを食べないと生きていけません。アルゼンチノサウルスは、アフリカゾウの5~6倍の大きさになります。これでは、どう頑張っても巨体を維持できません。そこで、アルゼンチノサウルスが手に入れたもの。反れが、体を大きくし、巨大な腸を獲得して、その中のバクテリアの力で消化することでした。そのため、アルゼンチノサウルスはいちいち植物を噛まなくても、そのまま丸呑みし、常にその巨体を維持することができたのです。肉食恐竜も攻撃をためらうほどにまで巨大化したアルゼンチノサウルス。この破天の超巨大竜を負かす力を持つ恐竜はそうそういないでしょう。
6位プエルタサウルス
アルゼンチノサウルスに匹敵する巨神
プエルタサウルスは、恐竜の中でも圧倒的な体格を誇ります。生存競争、つまり自然界では、体が大きいほど生き残る確率は高くなります。理由は簡単です。体が大きいほど捕食動物が被食動物を襲うリスクが高くなるからです。実際、竜脚類の化石から捕食動物が襲ったあとはほとんど見つかっていません。まあ超巨大竜脚類の化石は見つかっている量が少ないので、実際は頻繁に襲われていたのかもしれませんが…ただし、スピードや知能が極めて低いプエルタサウルスが後期白亜紀の絶対的支配者として君臨していたティラノサウルスや、私が制作したランキングでプエルタサウルスよりも上位にランクインしたアルゼンチノサウルスをも襲っていたと考えられているギガノトサウルス、そしてあのティラノサウルスをも超える可能性を秘めている悪霊・マイプにプエルタサウルスが敵うことはできないと判断したため、彼らよりも下位にランクインさせました。
前期白亜紀のアフリカの覇者
カルカロドントサウルスは、前期白亜紀のアフリカの王者でした。カルカロドントサウルスの強みは、攻撃力に特化した顎にあります。カルカロドントサウルスの咬合力はそこまで強くありません。そのかわり、カルカロドントサウルスには自分が傷つくことなく獲物を仕留める技がありました。カルカロドントサウルスの歯は、サメのように肉をそぎ取るのに適していました。ちなみに、カルカロドントサウルスの「カルカロドント」は、世界最大のサメであるメガロドンの学名、カルカロドン・メガロドンに由来しています。話が脱線してしまいましたね。気を取り直して。前述した通り、カルカロドントサウルスの歯は、肉をそぎ取るのに適していました。つまり、カルカロドントサウルスの狩りの方法は次の通りです。まず、狩りの鉄則通り弱いもの、幼いもの、そして負傷したものを狙います。そして狙いを定めると、ターゲットに突進します。次に、そのターゲットに勢いよくかみかかり、負傷させます。あとはターゲットが出血多量で倒れるのを待つだけ。ターゲットが倒れると、ターゲットにとどめを刺さず、そのまま肉を貪ります。カルカロドントサウルスは、貴重な獲物を決して逃さぬ冷徹なハンターだったのです。
8位アンキロサウルス
後期白亜紀の北アメリカの重戦車
アンキロサウルスの防御力は、恐竜界最強と言ってもいいでしょう。
「ジュラシック・ワールド」ではインドミナス・レックスに一瞬で
○されていましたが、それはインドミナス・レックスがチートと言っても過言ではないほどに強かっただけで、実際は簡単にはやられない
どころか、むしろ敵を返り討ちにすることができました。実際、
ティラノサウルス類のゴルゴサウルスの足の化石から、
アンキロサウルス類のズールにつけられたと見られる、怪我の跡が
見つかっています。化石にあとが残るほどの怪我を負わせるという
ことは、それだけのパワーと攻撃力を持っていたということ。
肉食恐竜も攻撃をためらったに違いありません。
まあ、ひっくり返されると、二度と起き上がれなかったと言われている
ので、この順位が妥当でしょう。
後期ジュラ紀の絶対的王者
サウロファガナクスは、アロサウルス類最大の体格を誇ります。アメリカにある、モリソン層という地層から発見されました。最初は、サウロファグスという名前で呼ばれていましたが、すでに鳥類にその名前がついていました。生物の名前は、先にある名前を残すというルールがあるため、サウロファグスから、サウロファガナクスという名前になりました。モリソン層の生態系の最上部に君臨し、当時のモリソン層のすべての生物を捕食対象とみなし、暇さえあれば生物を殺していたと考えられています。また、サウロファガナクスはある程度の知能や社交性もあったと考えられており、群れを作り、大まかな作戦を立てたうえで獲物を襲うことならできたと考えられています。
10位アルバートサウルス
俊敏性と攻撃力を兼ね備えた捕食者
アルバートサウルスは、ティラノサウルスよりも少し前の時代に生きていたとされるティラノサウルス科の捕食者でした。カスモサウルスやペンタケラトプス、エドモントサウルスなどを主食にし、当時の生態系の頂点に君臨し、基本的に不意打ちをして獲物を◯していたと考えられています。不意打ちで獲物を仕留めていた理由をお答えしましょう。アルバートサウルスの体は他の捕食者に比べ比較的華奢でした。そんなアルバートサウルスがカスモサウルスやペンタケラトプスと真正面から戦うとどうなるかわかりますよね?さらに言うと、アルバートサウルスはスタミナがそこまで高くありません。それに対し、植物食であるためにスタミナがあるカスモサウルスやペンタケラトプスと全う勝負を挑むと足に角を突き刺され、アルバートサウルスは倒れます。ですからアルバートサウルスは不意打ちをしていたと考えられているのです。そのために俊敏性を上げたのです。不意打ちをしても俊敏性がないと攻撃が当たらない可能性が高くなってしまいますからね。まあ狩りの仕方はカルカロドントサウルスと似ていますね。そういえばこのコメントを書いているときに気づいたんですが、このランキング、アルバートサウルスと互角の戦闘能力を持つとされるゴルゴサウルスがランクインしてない気がするんですけど…
11位ブラキオサウルス
後期ジュラ紀の高層タワー
ブラキオサウルスは、後期ジュラ紀最大級の大きさを誇っていた恐竜でした。全長は25メートル、体重は50トン。ブラキオサウルスは、恐竜好きでなくても知っている方が多いのではないでしょうか。当時の頂点捕食者であるアロサウルス、サウロファガナクス、トルヴォサウルス、ケラトサウルスに襲われることなど殆どありませんでした。なんせこんな巨体を一頭で襲うことなど無謀な行動としか言いようがありません。現代で例えれば…そうですね。スコティッシュフォールドが一匹でハイエナに挑む…ということでしょうか。そう、「一頭であれば」です。群れを作れば、捕食者にもブラキオサウルスに勝てる見込みができます。とはいえ、油断すれば、踏み潰される、または尻尾で場外ホームランになることになります。ブラキオサウルスは、捕食者を返り討ちに合わすことができる、恐竜界の摩天楼だったのです。
12位シアッツ
北アメリカの殺戮者
シアッツ…最近発掘が進んでいる種の一つですね。実はこのシアッツ、世界最大の肉食恐竜、スピノサウルスの最大肉食恐竜の座を大きく揺るがす恐竜として注目されています。なぜなら、初めて発見されたシアッツの化石は幼体のもの。幼体にもかかわらず、推定全長は9メートル以上。少なくとも、ティラノサウルスよりは明らかに巨大でしょう。前期白亜紀、ティラノサウルスの祖先がもともと生息していたアジアが大災害に見舞われ、ティラノサウルスの祖先が逃れてきた北アメリカ。しかしそこには、ティラノサウルスの祖先にとっては大災害に匹敵する恐ろしい生物がいました。それこそがシアッツです。当時のティラノサウルスの祖先の全長は5メートルほど。シアッツにとっては赤ちゃんにじゃれつかれているようなものだったでしょう。前期白亜紀の北アメリカではまさに幻想万華鏡の妖夢の「切れぬものなど…あまりない!」というセリフならぬ「私を倒せるものなど…あまりない!」と言わんばかりの力を振るっていたと考えられています。ただし、7000万年前にティラノサウルス・レックスが出現してからは話が変わっていきました。ティラノサウルスに瞬殺されるほどにまで立場が逆転し、最終的に絶滅したと考えられています。とはいえ、世界最大級の肉食恐竜になるかもしれないシアッツ。これからの新しい情報が気になるところですね〜
13位アクロカントサウルス
13位バリオニクス
前期白亜紀の水辺の狩人
バリオニクスは、前期白亜紀の狩人でした。基本、魚を狩っていました
が、胃の内容物から、植物食恐竜のイグアノドンの化石が見つかっている
ことから、恐竜をかることもあったと考えられており、恐ろしいハンター
として恐れらていました。
13位ステゴサウルス
13位リオプレウロドン
14位テムノドントサウルス
15位タルボサウルス
後期白亜紀のモンゴルの覇者
10メートルにもなるこの怪物の意味は、「恐るべきトカゲ」。
その名の通り、当時のモンゴルの生物から恐れられていたと考えられていて、当時の生態系の頂点に立っていたと言われています。
15位ケラトサウルス
ケラトサウルス(Ceratosaurus)は、中生代ジュラ紀中期から後期 (約1億5,300万~約1億4,800万年前) にかけての現在の北アメリカ大陸とアフリカ大陸に生息していた獣脚類の恐竜の一種。竜盤目 - 獣脚亜目 - ケラトサウルス科に属する。属名は「角をもつトカゲ」を意味する。nasicornis種は北米で保存状態のよい化石が見つかっている模試種である。 ingns種は東アフリカ産で、dentisulcatus種及びmagnicornis種は共に北米産であり、いずれもnasicornis種よりも大型である。特にingns種は非常に大型だったことが推定されるも、化石が断片的であるため、ケラトサウルス属に含むことを疑問視する学説もある。
中期ジュラ紀の捕食者
ケラトサウルスは、大きく鋭い歯をあごに並べた森のハンターでした。
中期ジュラ紀の生態系の頂点に立っていましたが、後期ジュラ紀には
アロサウルス、トルボサウルス、サウロファガナクスに
頂点の座を奪われ、末期ジュラ紀に姿を消しました。
15位ユタラプトル
ラプトル界屈指の戦闘能力(メガラプトル類を除いては)
ユタラプトルの名前の意味は「ユタ州の略奪者」。当時のユタ州の生態系の頂点に君臨し、ガストニアなどの中型装甲植物食恐竜などを捕食していたと考えられています。(ガストニアに返り討ちに合うのがほとんどだったみたいだけど)長い間ラプトルの中で最大最強と考えられていましたが、その名誉は今ではもう別の種類に奪われてしまっています。その種類は言わなくてもわかるでしょう。そう、メガラプトル類です。メガラプトル類に属すメガラプトル、ライトニングクロー、アウストラロベナトル、フクイラプトル、マイプ・マクロソラックスの中でもマイプ・マクロソラックス(以下、マイプ)。ただでさえメガラプトル類の体格はユタラプトルにとって脅威だというのに。マイプの体格は10m。これだけでもユタラプトルの勝利は絶望的。さらにいうと、マイプの鉤爪。30cmもの長さがあるだけのことはあります。攻撃範囲が広く、そもそも近づくことができません。まあそれでもユタラプトルはラプトル界の副隊長を補っています。
16位マプサウルス
17位テリジノサウルス
強くはない
巨大な鉤爪を持つテリジノサウルス。その姿はいかにも強そうですが、
実はあまり強くありません。テリジノサウルスの爪は、骨の構造上、
全く曲がらないことがわかっています。
また、テリジノサウルスはお腹が大きいため、いざという時に
逃げることができません。
以上がテリジノサウルスが弱いと思う理由です。
17位アパトサウルス
18位ヴェロキラプトル
ヴェロキラプトルはまあ…強いんじゃない?
単体では最弱レベルですが、集団ではそれなりに強いのではないでしょう
か。
しかし鉤爪が脆いなどの弱点も多くあるため、集団だけでここまで
上位に食い込むことは難しいのではないでしょうか。
18位カルノタウルス
もうちょっと順位低くてもいいんじゃない?
咬合力が低いのと、前足が小さいのが気になりますね。
多分マイプのほうが強いので、マイプを3位に上げ、カルノタウルスを
現在のマイプの順位におろしたほうがいいと思います。
あ、それとこのランキングに入ってる恐竜の中に同じ種が2匹入ってたり、実在していなかった恐竜を見つけたときは、基本的に10点にしますのでそこんとこよろしくです。例えばまいぷ(このコ今35位だしなぜひらがなになっている)とかクリスタトゥサウルス(ズールの名前を勝手に変えるなし!あと当然のように同じ種が同じランキングに2匹いるのなあぜなあぜ)とかです。そのような種にはコメントのどっかに✓マークを付けときます。
19位アロサウルス
アロサウルス(Allosaurus、“異なるトカゲ”の意、かつての和名は異竜)とは、中生代ジュラ紀後期(約1億5,500万 - 1億5,000万年前)の北アメリカに生息していた大型肉食獣脚類に属する恐竜である。1877年にアメリカ合衆国の古生物学者オスニエル・チャールズ・マーシュがこの種を定義づける化石を初めて報告した。肉食恐竜としてはティラノサウルスと共に恐竜研究の興隆期からよく知られたものの1つであり、古生物学を専業とする人々以外にも映画やドキュメンタリーを通して有名な存在である。また日本では、国内で最初の恐竜の骨格標本展示として1964年に国立科学博物館で標本が公開された。のち、2015年7月の地球館展示リニューアルに伴って1階に常設展示が始まった。
後期ジュラ紀には爬虫類を喰らう王者がいる…
アロサウルスがここまでランキング上位に入ってくるのはおかしいと
思います。後期ジュラ紀には、他にもトルボサウルスやケラトサウルス、
サウロファガナクスがいました。中でもサウロファガナクスは、
アロサウルス類最大の体格を誇ります。アロサウルス類で最大の体格を
誇っているにも関わらず、アロサウルスが圧勝するのはおかしいです。
20位トリケラトプス
全く強くない
トリケラトプスの化石にティラノサウルスの噛み跡が残っていることが
弱いと思う理由です。ティラノサウルスは知能が高く、獲物の弱点を
正確に見抜き、そこを集中的に攻撃することができたと考えられて
います。しかし、トリケラトプスは弱点に噛み跡が多く残っていること
から、トリケラトプスは弱点を守ることができなかったと考えたから
です。
21位ケツァルコアトルス
いやまあ天空の王者なんだけどさ
たしかにケツァルコアトルスは天空の王者の名をほしいままにし、空中で暴れまわっていたと考えられていますが、私的にはもうちょい順位が低くてもいいと思います。ケツァルコアトルスが弱いと言いたいわけではありませんが、咬合力がなさすぎることと、骨が華奢すぎることが挙げられますね。それからもう一つ。最近の研究では、そもそもケツァルコアトルスが飛べないと言われ始めていることです。2022年、名古屋大学は今まで見つかっている全ての飛行ができるとされる古代から現代までの生物の飛行能力を物理学的に検証しました。その結果、ケツァルコアトルスの飛行能力は、他の生物に比べてダントツに低いということがわかりました。まあ地上を歩き回って生物を捕食していたとしてもそれはそれで十分の脅威です。なんせ数mの高さからクチバシが雨のように振り下ろされるんですから。まあこれくらいですかね。
21位プテラノドン
21位イグアノドン
21位ブロントサウルス
21位パラサウロロフス
21位スティラコサウルス
21位アノマロカリス
待ってどーゆーこと?
アノマロカリスは節足動物亜目アノマロカリス科に
属すグループで恐竜ではありません。一応海竜などの恐竜以外の生物も解説するつもりですが、こいつだけは見逃せません。
結論アノマロカリスをランキングから外せ!
21位クリスタトゥサウルス
23位パキケファロサウルス
んー
パキケファロサウルスは頭突きができるという考えが定着しているようですが、実際は頭突きができないと考えられています。最近の研究では、パキケファロサウルスの頭骨には血管が張り巡らされており、頭突きをすれば脳挫傷を起こすか頭が割れて大出血すると考えられています。
24位スピノサウルス
最弱だよね?(スピノファンの皆様申し訳ございません)
スピノサウルス推しの方々には申し訳ないですが、あなた達の心を全力でへし折りに行きたいと思います。おっと。その前に。今回スピノサウルスとスペックを比べる恐竜の名前を書いておきます。
ティラノサウルス
カルカロドントサウルス
ギガノトサウルス
アルゼンチノサウルス
アンキロサウルス
マイプ
サウロファガナクス
アロサウルス
まず、スピノサウルスの歯。そもそもの性能が他の恐竜よりも劣っているように感じます。スピノサウルスの歯は、肉を切り裂いたり、噛み砕いたりすることに適していません。魚の硬い鱗を叩き割るのに適していました。さあ、魚の鱗と恐竜の皮膚。どちらのほうが防御性能が高いでしょうか。一度聞いたぐらいでは、「魚の鱗のほうが硬いに決まってんだろ!」と答える人が多いと思います。しかし、恐竜の中にも防御性能が高いものは山ほどいます。今回スペックを比べる恐竜の中で防御性能が高いもの。それは、アンキロサウルスとアルゼンチノサウルスです。彼らの防御性能は、もはや神の領域と言っても過言ではないないでしょう。攻撃が効かないようじゃ、スピノサウルスと彼らが戦ったとしてもスピノサウルスの敗北は決定的です。これでスピノサウルスはアンキロサウルスとアルゼンチノサウルスには勝てないことがわかりましたね。これはティラノサウルス、カルカロドントサウルス、ギガノトサウルス、マイプの4体にも言えることです。彼らの歯は、噛み砕く、または切り裂くのに適していました。カルカロドントサウルス、ギガノトサウルス、マイプには巨大な鉤爪もあるため、スピノサウルスは攻撃力の点でまず勝つことはできないでしょう。残りのアロサウルスとサウロファガナクス。スピノサウルスが勝てる見込みはあるのでしょうか。スピノサウルスは走ることができません。なぜかって?スピノサウルスは主に水中で暮らしていました。それをいいことに、水中に相手を引きずり込み、そのまま一方的に相手を打ちのめす。たしかにスピノサウルスほどのパワーがあれば引きずり込むこともできるかもしれませんが、水中生活に適応した結果、足の骨がもろくなったのです。答えは簡単。水の中で浮力を得るために全身の骨の内部を空洞化させたからです。走ることができないようでは、スピノサウルスがアロサウルスやサウロファガナクスと戦ったとしても、身軽かつ俊敏、スタミナも充分にある2頭には攻撃が当たらないままズタボロにされ、そのまま出血多量で天に召されてしまうでしょう。スピノサウルス推しの皆さん。これでスピノサウルスはそこまで強くないということがおわかりいただけたでしょうか。
ライフスタイルの新着記事
おすすめのランキング




あわせて読みたいランキング






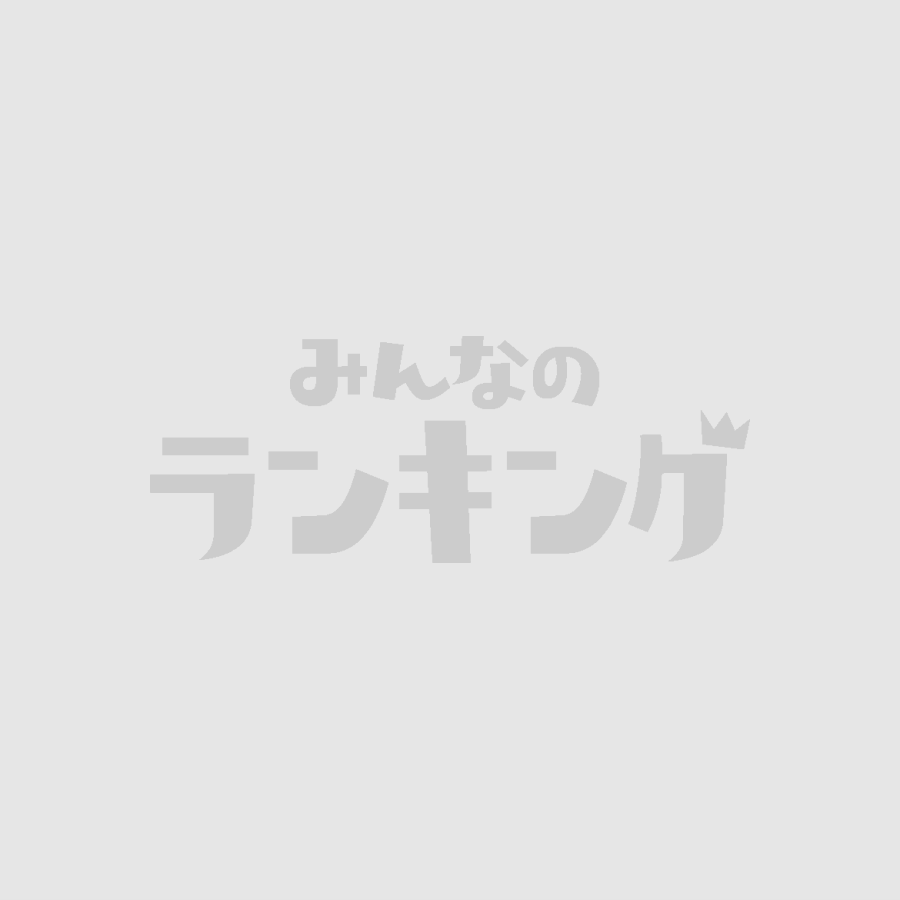












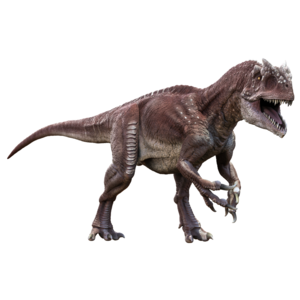









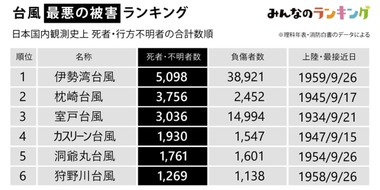




水中の完全捕食動物
低評価の人たちの言う通り、恐竜ではありませんが、白亜紀の海の絶対的王者であった事は間違いありません。赤ちゃんのときはどうだったんだって言われるとあれですが、成体になればもはや敵なしです。モササウルスの強さを表せって言われたら私はこのような表し方をします。
ティラノサウルス+プルスサウルス÷2✕リオプレウロドン+バショウカジキ÷2=モササウルス1体
です。(これは完全個人の表し方です。)また、モササウルスには獲物を大量に確保できる技がありました。モササウルスの下顎の骨には関節があり、口を開くと同時に下顎の面積が広がり、水ごと獲物を吸い込む。これを使い、獲物を大量に確保することができ、モササウルスは全長を18メートルまで巨大化することができたのです。しかし、モササウルスの先祖もここまで強かったのでしょうか。残念ながら、モササウルスの先祖は強くなかったと考えられています。モササウルスの先祖は全長1メートル。アルヴァレスサウルスは愚か、何ならコンプソグナトゥスよりも弱かったかもしれません。そこで、モササウルスの先祖が取った行動。それが、海を住処にすることでした。また、モササウルスの先祖が海に進出した頃、海にはモササウルスの先祖の脅威になる生物がほとんどいませんでした。そのため、モササウルスの先祖はやりたい放題に進化し、最終的に海の絶対的王者へと上り詰めたのです。
おまけ モササウルスの仲間を知ってる限り出してみよう!
1モササウルス
2ティロサウルス
3アイギアロサウルス
4カーソサウルス
5ダラサウルス
6プラテカルプス
7プログナソドン
8グロビデンス