ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位織田信長
2位武田信玄
統率力、武勇、知略、政略全てにおいてトップレベル
氾濫が起きやすい川を堤防で押さえることに成功した。これを信玄堤と言う
甲斐の戦国大名
本拠地は躑躅ヶ崎館
農本主義的大名
甲斐の虎と呼ばれた彼の率いる武田軍は当時最強と言われ、その武勇はのちの天下人織田信長の耳にも届き、恐れさせるほどでした。天下を目指していた武田信玄が、上洛を前に病に倒れることがなければ、日本の歴史は変わっていたかもしれないとも評されています
3位北条早雲
戦国時代は北条早雲の下剋上から始まったと言われています
戦国時代に相模国(さがみのくに:現在の神奈川県)を統一した人物。小田原城の城主で、鎌倉幕府の執権・北条氏とは全く関係はありません。鎌倉時代に活躍した北条氏と分けるため、「後北条氏」や「小田原北条氏」と呼ばれます。なかでも北条早雲は、「戦国時代は北条早雲の下剋上から始まった」と言われるほどの戦国武将です。一介の浪人から戦国大名へと成り上がったと描かれることも多い
4位徳川家康
敗戦の多い徳川家康だが小牧長久手の戦いでは見事に勝利を収める
1564年(永禄7年)、「三河一向一揆」を鎮圧させて、その勢いのままに東三河・西三河を平定。無事に三河国を統一した徳川家康は、1566年(永禄9年)に朝廷から「従五位下三河守」(じゅごいのげみかわのかみ)に叙任されて、松平姓から「徳川」姓へと改めました。
徳川家康にとっての最大の負け戦と言えば、甲斐国(現在の山梨県)「武田信玄」と激突した「三方ヶ原の戦い」です。
1572年(元亀3年)、甲斐を出発した武田信玄が北近江の浅井氏、越前の朝倉氏、そして大坂の石山本願寺・反織田勢力と結託して信濃から遠江国(とおとうみのくに:現在の静岡県西部)に侵攻。徳川家康を牽制する目的で二俣城(ふたまたじょう)を陥落させます。二俣城が落ちたことで、徳川家康が本城としていた浜松城は、掛川など東部拠点との連絡線を絶たれて窮地に陥りました。
徳川家康は、次に武田軍に攻め込まれるとすれば浜松城だろうと予測を立てて、浜松城に籠城します。このとき、織田信長からの援軍と徳川家康軍合わせて約11,000人。これに対して武田軍は約30,000人の軍勢を率いており、多勢に勝利するには籠城戦が最適だったのです。
しかし、ここで武田軍が思わぬ動きを見せました。浜松城へ向かっていたはずの武田軍が突如進路を変えて、三河国(現在の愛知県)方面へと進撃を開始したのです。戦国時代において、進行上の城へ攻め込まないというのは異例の事態でした。武田信玄による目に見えた挑発行為でしたが、徳川家康はこの挑発に乗ってしまいます
最初こそ徳川家康軍が優勢を取っていましたが、戦力差による不利が次第に見え始め、ついに徳川家康は敗走。辛くも浜松城へ逃げ帰ったというのがこの戦いの顛末です。この敗走で、徳川家康を守るために有力な家臣が多く戦死しています。
「本能寺の変」で織田信長が「明智光秀」(あけちみつひで)に討たれる前日、徳川家康は堺で商人と茶会を開いていました。茶会の翌日、上洛しようとしていたところで織田信長の訃報を聞き付けます。
このとき、徳川家康が伴っていた従者は30名余り。その中には、「徳川四天王」として名高い「本多忠勝」や「井伊直政」など、有力な家臣も多くいました。しかし、僅かな手勢であったため大軍に襲われればひとたまりもありません。徳川家康は、家臣からの説得に応じると三河国へ帰国することを決意します。
これは、「神君伊賀越え」と呼ばれる徳川家康にとっての災難のひとつ。この時点で危惧しなければならないのは、明智光秀の手の者だけではなく、織田信長の去就定まらない家来、在地の土豪や百姓達の襲撃。特に、自分達の村を侵入者から守るために武装した農民による落ち武者狩りは脅威でした。事実、明智光秀は織田信長を討ったあとに落ち武者狩りに遭い、その際の傷が致命傷となって命を落としています。
武装する農民達を退け、道中では織田家の家臣「長谷川秀一」や「西尾吉次」などに助けられながら険しい道を乗り越えた徳川家康一行は、無事に三河国へ到着。そして徳川家康は、出世頭であった豊臣秀吉が、天下取りに向けて織田信長の家臣と戦を繰り広げる様子を一旦見守ることになります。
本能寺の変以降、徳川家康は領主不在の甲斐・信濃・上野を攻略するために北条氏と同盟・縁戚関係を結び、遠江・三河と併せて5ヵ国の大大名に上り詰めました。
そして1584年(天正12年)、徳川家康は、織田信長の死後に豊臣秀吉と対立するようになった織田信長の2男「織田信雄」(おだのぶかつ)の救援のために豊臣秀吉軍と対峙することになります。
「小牧・長久手の戦い」と呼ばれるこの合戦は、約16,000人の徳川家康・織田信雄軍に対して、豊臣秀吉軍は約100,000人と兵力に大きな開きがありましたが、小牧山での奮戦により豊臣秀吉軍を撃退。続く長久手の戦いで徳川家康軍が豊臣秀吉軍を襲撃し、豊臣秀吉軍の「池田恒興」(いけだつねおき)、「池田元助」(いけだもとすけ)、「森長可」(もりながよし)を討ち取ります。連戦連勝の豊臣秀吉軍にとっては手痛い敗北でした。
その後、約8ヵ月に及んだ小牧・長久手の戦いは、豊臣秀吉から講和を持ちかけられた織田信雄が受諾する形で終結。織田信雄の援軍という名目で参戦していた徳川家康は、戦う理由を失ったために三河へと帰国しました。
1586年(天正14年)になると、豊臣秀吉は徳川家康を服属させようと接近します。臣従することを拒否していた徳川家康に対して、豊臣秀吉は実妹「朝日姫」を後妻として差し出し、義兄弟になりました。
その後、徳川家康は大坂城で豊臣秀吉に謁見。譜大名の前で忠誠を誓い、1590年(天正18年)の小田原征伐には豊臣秀吉軍として参戦し、大きな戦功を挙げます。
関東8ヵ国を拝領した徳川家康は、関東の領地経営や軍制改革に専念し、有力な家臣を各地に配置するなどして難なく統治を実現しました。
豊臣秀吉の狙いは、大きくなった徳川家康の力を削ぐためでしたが、豊臣秀吉の思惑とは裏腹に次第に関東での支配力を拡大。徳川家康は、武田軍の旧家臣や北条氏の家臣を迎え入れ、申し分ない軍事力を蓄えていったのです。
関東で着実に力を付けていった徳川家康は、1598年(慶長3年)に豊臣秀吉が没すると、いよいよ天下取りの最後の仕上げに踏み切ります。
徳川家康は、豊臣秀吉の遺言により「五大老」の筆頭に着任。豊臣秀吉の遺言である「諸大名同士の結婚の禁止」を破って「福島正則」らと婚姻関係を結ぶ他、禄高(ろくだか:武士の給料)の増減に関与するなど、豊臣秀吉政権に反発する動きを見せます。
そんな徳川家康の暴走を見かねて立ち上がったのが、「五奉行」の筆頭に就いていた豊臣秀吉の重臣「石田三成」。
徳川家康は、天下を取るにあたり、石田三成が障害になると見越しており、石田三成を失脚させるために、「加藤清正」や福島正則を味方に付けました。
1600年(慶長5年)、五大老のひとり「上杉景勝」に謀反の疑いがあるとして、徳川家康は討伐軍を結成。「会津征伐」と言われるこの挙兵は、のちに起きる「関ヶ原の戦い」のきっかけと言われています。
上杉景勝を討伐するために会津へと向かう途中で、徳川家康の耳に石田三成らの挙兵の報せが入りました。徳川家康は、会津への進軍をただちに取りやめると、石田三成討伐へと動き出します。豊臣政権や石田三成らに反感を抱いていた諸大名を招集して東軍を結成。石田三成は、豊臣政権を守るために徳川家康率いる東軍と衝突します。
天下分け目の戦いは、美濃国(現在の岐阜県)「関ヶ原」で繰り広げられました。開戦当初は西軍側が優勢でしたが、次第に西軍側から東軍側へ寝返る兵が増えていきます。本戦開始から約6時間後、混乱を極めた戦場で西軍側の諸将が次々と敗走。
そして、松尾山で傍観していた西軍の「小早川秀秋」が東軍へ寝返り、西軍「大谷吉継」隊へ攻め込みました。これが決定打となり、徳川家康率いる東軍は勝利を収めます。合戦から数日後、逃亡していた石田三成は捕縛され、京都の六条河原で処刑されました。
5位毛利元就
権謀術に長けた大名
安芸国の国人領主から、中国地方全域を統一した戦国時代の豪傑。幼少期に両親を失い、19歳で兄を失い、さらに甥までをも亡くしたことで、次男にして毛利家の家督を相続します。権謀術に長け、稀代の策略家としても有名な武将です。
これにより、毛利元就は幸松丸に代わって、吉川氏援護のために出陣。吉川氏と共に安芸武田氏と戦いました。これが「有田中井手の戦い」です。毛利元就にとっては初陣でした。
毛利元就は、初陣にもかかわらず、安芸武田氏の重鎮にして猛将と言われた「熊谷元直」(くまがいもとなお)を討ち取り、さらには武田元繁までも討ち取る大勝利。敵軍安芸武田氏の5,000の兵に対し、毛利側は1,200~2,000の兵に過ぎなかったことから、毛利元就の名は広く知られることになりました。そのため、後世においてこの戦は、毛利家の「明」と安芸武田家の「暗」を分ける「西国の桶狭間」と言われるようになります。
その後も、毛利元就は後見役として尽くし、大内氏から尼子氏へ従属先を変えたり、戦に出向いたりなど、毛利家存続のために奮闘しました。しかし1523年(大永3年)、幸松丸が病気で他界し、毛利元就は27歳にして毛利家の家督を継ぐことになったのです。
家督相続の少し前から、大内氏から離れ尼子氏に付いていた毛利元就でしたが、幸松丸の死去による家督継承をめぐって、「尼子経久」(あまごつねひさ)と対立するようになっていました。
他にも十分な恩賞が得られないなどの不満があり、毛利元就は徐々に尼子経久と距離を置くようになります。
家督相続から2年後の1525年(大永5年)、毛利元就は大内義隆の傘下に入ることを明言します。毛利元就は大内氏の下、安芸と備後両国の軍事を指揮するようになりました
6位豊臣秀吉
賤ヶ岳の戦いの柴田勝家との一戦に勝ち天下人となった
戦国三英傑の1人に数えられている戦国武将です。豊臣秀吉は農民の出身でしたが、数々の武功を挙げた上に本能寺で織田信長を暗殺した「明智光秀」を討ち取ります。その後、清洲会議で対立した「柴田勝家」に勝利すると、「毛利輝元」(もうりてるもと)や「小早川隆景」(こばやかわたかかげ)らを取り込み勢力をさらに拡大し、ついには天下人・関白まで上り詰めました。「墨俣一夜城」(すのまたいちやじょう)や「金ヶ崎の退き口」(かねがさきののきくち)など様々な逸話を残した
1554年(天文23年)、豊臣秀吉はこの頃から「織田信長」の奉公人として仕えます。
1561年(永禄4年)、足軽組頭まで上り詰めた豊臣秀吉は、足軽組頭として同じ長屋に住んでいた「杉原定利」(すぎはらさだとし)の娘「ねね」と婚姻。その後、豊臣秀吉は様々な偉業を成し遂げていきます。
1566年(永禄9年)、美濃国(現在の岐阜県)斎藤家へ侵攻する際に、敵前で一夜にして「墨俣城」を築き上げたという「墨俣一夜城」。川の上流から木材を流し、下流で築城を進めるという奇策は、豊臣秀吉の存在を織田信長に示した最初の功績と言われています。
さらに、1570年(元亀元年)の越前国敦賀郡(えちぜんのくにつるがぐん:現在の福井県)で起きた「金ヶ崎の戦い」では、「金ヶ崎の退き口」(かねがさきののきくち)という撤退劇を披露し、功績として黄金数十枚を賜っています。
1572年(元亀3年)、豊臣秀吉は「丹羽長秀」や「柴田勝家」のような人物になると誓い、2人の名前を取って「羽柴秀吉」に改名。1575年(天正3年)の「長篠の戦い」では、「霧山城」を攻め落とす活躍を見せるなど、徐々に頭角を現していきました。
しかし、その矢先の1577年(天正5年)、豊臣秀吉の進退に大きな影響を及ぼす出来事が起きます。加賀国(現在の石川県南半部)「手取川の戦い」の際、作戦に関する意見の食い違いにより柴田勝家と揉めて、豊臣秀吉は無断で兵を撤収。その結果、柴田勝家は「上杉謙信」に敗北してしまい、このことが織田信長に知られると、豊臣秀吉は激しく叱責されてしまいました。
7位明智光秀
私の本心を知らない人から何と言われようと構わない。この命も名誉もすべて惜しくはない
私の本心を知らない人から何と言われようと構わない。この命も名誉もすべて惜しくはない」との名言を残した
丹波平定で戦上手でもあり、家中軍法でもわかるように政治力もある。秀才
出自は、美濃国土岐(現在の岐阜県南部)の庶流であったと考えられている。
本圀寺の変にて、窮地に陥った足利義昭の危機を救ったのが明智光秀でした。明智光秀は、細川藤孝や池田勝正達と協力して三好三人衆を退けました。
その後京都奉行の職務を任されることになります。
金ヶ崎退き口という撤退戦で羽柴秀吉と共に殿を務め奮闘しました。その後織田信長から褒美として宇佐山城を任されることになりました。その後、明智光秀は比叡山延暦寺焼き討ちで実行部隊の中心として活躍。
さらに、長篠の戦い、天王寺の戦い、有岡の戦い、信貴山城の戦いなど数々の戦に参戦。
四国全土を領有しようとする長曾我部元親と南半分にせよと命令する織田信長の仲介役としての仕事も任されました。
「私の本心を知らない人から何と言われようと構わない。この命も名誉もすべて惜しくはない」といった名言を残しました
18 条からなる家中軍法は、明智光秀が本能寺の変の1 年前に福智(知)山城で制定したものといわれています
8位北条氏康
統率力と政治力に長けた武将
桓武平氏の流れを汲む、相模の名門の家柄。
北条家と言えば、桓武平氏の流れを汲む、相模の名門の家柄。
郡の制圧時に集落の掌握・建設状態を維持、用兵 敵部隊を挟撃中、自部隊の攻撃上昇、作事 城下施設の建設効率上昇と言うように統率力と政治力に長けた武将であり、武力、知略もそこそこ、総合力ではトップ10に入る大名であろう
9位上杉謙信
武田、北条、織田なと、数々の戦をし、その勝率97%。あまりの強さに「軍神」と言われるようになった
戦の勝率が97%だったと言われています。
本拠地春日山城
越後国山内上杉家16代当主の戦国武将です。
結果は、長尾景虎軍の圧勝。続く第二次川中島の戦いでも、川中島の所領を領主に返すという有利な条件を引き出し、長尾景虎軍が勝利します。
1557年(弘治3年)の第三次川中島の戦いでは、長尾景虎軍は武田領内に深く進軍し、武田軍も決戦を避ける形で守りを固め、膠着状態のまま戦いが終わりました。
1559年(永禄2年)、長尾景虎は2度目の上洛を果たし、「正親町天皇」(おおぎまちてんのう)や将軍・足利義輝に拝謁。足利義輝から管領並みの待遇を受けたと言われています。
1560年(永禄3年)5月、「桶狭間の戦い」によって「甲相駿三国同盟」の一角が崩れたのをきっかけに、長尾景虎は北条氏康の討伐を決断しました。越後国から関東へ向かう道中、上野国(現在の群馬県)箕輪城主「長野業正」(ながのなりまさ)の支援を受けながら北条方の諸城を次々と攻略。関東に拠点を作り、徐々に北条軍を追い詰めていきます。
そのまま機を伺いながら年を越しますが、その間に北条討伐に向け関東諸将らの協力を仰ぎ、ついに武蔵国(現在の東京都、埼玉県、神奈川県北東部)へ進軍を開始
武蔵国の各城を配下に治めつつ小田原城を目指し、10万もの軍勢で小田原城を含めた諸城を包囲して、攻撃を開始しました。長尾景虎の猛攻により、北条氏康が籠城を決断するまで追い込むことに成功したのです。
しかし、勝利を目前にした状況で、長期出兵を維持できない軍が無断で陣を引き払い、結果的に戦力は減少。さらに、武田信玄が動きを見せることで、長尾景虎軍は背後への牽制も余儀なくされ、戦況は膠着状態へと一転します。1ヵ月に亘る包囲も実を結ばず、長尾景虎軍は鎌倉へ撤退したのです。
1561年(永禄4年)、長尾景虎は上杉憲政の要請で山内上杉家の家督と関東管領職を相続しました。そして、名前を「上杉政虎」(うえすぎまさとら)へ改名。
10位伊達政宗
独眼竜
独眼竜政宗の異名で知られる出羽国出身の戦国武将。17歳で奥州伊達氏の家督を継ぐと、19歳で南奥州を支配し、仙台藩初代藩主となって東北の繁栄を築きました。あと10年、20年生まれるのが早ければ天下人となっていたかもしれないと言われる伊達政宗は、謝罪と処世術の達人でした。
11位真田昌幸
真田 昌幸(さなだ まさゆき)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。 甲斐国の武田信玄の家臣となり信濃先方衆となった地方領主真田氏の出自で、真田幸隆(幸綱)の三男。信玄・勝頼の2代に仕え、武田氏滅亡後に自立。織田信長の軍門に降り、滝川一益の与力となったが、本能寺の変後に再び自立し、近隣の北条氏や徳川氏、上杉氏との折衝を経て、豊臣政権下において所領を安堵された。上田合戦で2度にわたって徳川軍を撃退したことで、徳川家康を大いに恐れさせた逸話で知られるが、関ヶ原の戦いで西軍についたために改易された。 軍記物や講談、小説などに登場したことで、後世には戦国時代きっての知将・謀将としての人物像としてよく知られ、武田二十四将の一人にも数えられることがある。子に真田信之(上田藩初代藩主)、真田信繁(真田幸村)ほかがいる。他にもお初という織田信長の使いに入った真田の子という説もある
知勇兼備
94、80、99、85
知勇兼備、武田氏が滅びた後、織田信長に従属した。上杉景勝と同盟を組み、徳川氏と対峙出来る構図にした。その後も豊臣秀吉の与力となり、幾度も窮地を切り抜ける。この立ち回りは賞賛に値します。大好きな武将です
12位島津義弘
島津の退き口
95、93、84、80
島津の退き口
1572年(元亀3年)伊東義祐が3,000の大軍を率いて攻めてきました。いわゆる木崎原の戦いです。敵方の攻撃に対して、島津義弘は、わずか300の兵でこれを打ち破りました。このとき採った戦法が「釣り野伏せ」です。釣り野伏せとは、隊の配置を左右と真ん中にし、左右の隊はあらかじめ隠れておきます。真ん中の隊は敵の正面に激突させ、押されているふりをして退却し、追撃してきた敵を隠れていた左右の隊で挟み撃ちにする戦法です。真ん中の隊も攻撃に転じれば、左右、正面の3方向から攻撃できます。
この戦法は、少数で大軍を殲滅させるのに有効でした。島津軍は、釣り野伏せ戦法を効果的に使いこなすことで、数の上では不利な戦を何度も勝利することになります。
耳川の戦いで大友宗麟に大勝
「島津家久」(しまづいえひさ)は、決戦の地を湿地帯である沖田畷(おきたなわて:現在の長崎県島原市)に選定。兵力に勝る龍造寺軍をおびき出し、殲滅(せんめつ:残らず滅ぼすこと)させる作戦を採ることに決めました。
島津軍は、龍造寺軍が攻めてくると、おびき寄せるため応戦することなく退却。それを追撃してきた龍造寺軍に伏兵が鉄砲や弓を打ち込む奇襲攻撃で、龍造寺軍にダメージを与えました。龍造寺軍は、前線が退却しているにもかかわらず、後方に控えていた部隊が前進。これにより、身動きが取れなくなるなど、大混乱に陥ります。この戦いで龍造寺隆信は討ち取られ、沖田畷の戦いは、島津・有馬連合軍の大勝利となりました。
沖田畷の戦いの勝利によって、島津氏の勢力は北九州まで拡大。九州には島津氏に対抗できる勢力はなく、九州統一目前という状況でした。
朝鮮・明軍は島津義弘の戦いを見て鬼島津を名付け恐れました。
島津の退き口として有名な退却作戦など、逸話は数知れない。秀吉軍20万に対して最後まで戦うことを諦めなかった九州の勇将。大好きです
15位立花宗茂
西の立花宗茂、東の本多忠勝と言われ、戦の天才であった
87、98、82、62
「戦いは兵数の多少により決まる物ではない」との名言を残している
九州勢の中で非常に活躍した戦国武将のひとりです。
九州征伐で武勲を立てた立花宗茂は、豊臣秀吉より所領を授かり大名に出世。一介の家臣だった者が大名に出世することは、当時では異例の出来事でした。その後も、朝鮮出兵に参加するなど、豊臣秀吉が亡くなるまで、活躍を見せています。
豊臣秀吉が生前、東の本多忠勝、西の立花宗茂と評していたことから、徳川家康も立花宗茂を警戒していたようです。立花宗茂は、豊臣秀吉が亡くなったあとも、豊臣秀吉に対する恩義を重んじる人物でした。
16位本多忠勝
西の立花宗茂、東の本多忠勝と言われ、戦の天才であった
85、98、79、60
東の本多忠勝
本多忠勝は、生涯をかけて徳川家康に奉公し徳川幕府250年の天下の基礎を築いた戦国武将です。
徳川四天王、徳川三傑、徳川十六神将のひとりであり、徳川家臣最強の武将であったと語り継がれています。日本三名槍のひとつである「蜻蛉切」(とんぼきり)を愛刀としていた武将です。
単騎で朝倉軍に正面から突入した姉川の戦いや武田軍から徳川家を守った一言坂の戦いなどで武功を上げた本多忠勝の強さはまさに別格。生涯で57回もの戦闘に参加したにもかかわらず、傷ひとつ負わなかったという逸話があります。
17位加藤清正
かの熊本城を築城した武将
82、89、78、70
勇猛果敢で戦国武将の名にふさわしい猛将というイメージですが、実は武芸だけでなく、築城や領地統治などにも手腕を発揮しました。また、一時は石田三成との対立から徳川家康に与しましたが、亡くなる直前まで豊臣家の行く末を案じていた義に厚い武将です。
18位赤井直正
丹波の赤鬼
76、87、79、45
「丹波の赤鬼」と言われ恐れられた。
明智光秀の氷上郡侵攻に対し、直正は黒井城に籠城し、2ヶ月以上が経とうとした頃、波多野秀治が突如、反旗を翻して、明智軍を急襲。赤井、波多野軍に三方から攻め立てられた明智軍を敗走させた。
19位斎藤利三
明智光秀が織田信長に殴られてでも家臣に置いておきたい人物だった。
79、75、74、49
明智光秀が織田信長に殴られてでも家臣に置いておきたい人物だった。
1580年(天正8年)、光秀が苦労して手に入れた丹波の「黒井城」の運営は、利三に任されました。
この黒井城の場合、長い攻防戦の結果、城門や城壁はボロボロ。周囲の民家は焼け、田畑も荒れ果てていました。そんな状態で城に入った支配者を、住民が歓迎するはずがありません。そんななかで斎藤利三は、城の近くにあった屋敷を修復して拠点とし、様々な政策を打ち出しました。例えば明智軍が基地として使った寺に「人足役」(にんそくやく:税として課される労働)を免除する政策には、地元の人々と上手くやっていこうとした斎藤利三の苦労がしのばれます。戦で手に入れた国の運営は、ある意味、城を落とすよりも難しい仕事だったのです。
光秀が信長に対して謀反を起こそうとした時、斎藤利三は断固反対していました。
本能寺の変にて、光秀が利三の言うことを聞いて山崎で迎え撃つよりも坂本城に籠って戦えば、良いと進言したが却下されました。
斎藤利三の進言をどちらかでも許可していれば光秀にとって良い結果になったかもしれない程の金言でした。
20位和田斉頼
赤井氏に従うようになった和田斉頼
丹波に根を下ろした斉頼は永正十三年(1516)、山ノ峯(蛇山)に岩尾城を築くと、近隣を侵略して所領を拡大、市場之庄を「和田庄」と改めた。さらに領内の新田開発に着手、隣郷の久下氏と水争いを起こした。赤井氏の仲裁で事なきを得ると新田を拓き、三千七百余石を領する勢力となった。以後、和田氏は赤井氏に従うようになった
ライフスタイルの新着記事
おすすめのランキング


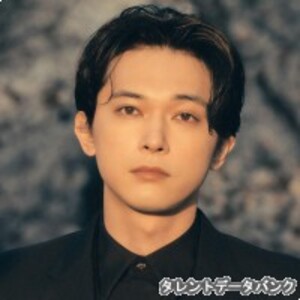

あわせて読みたいランキング
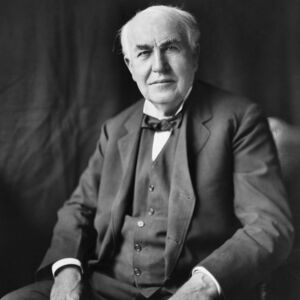



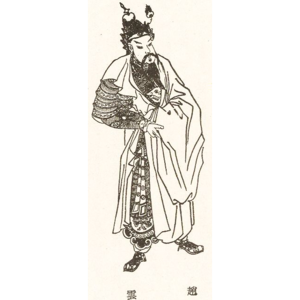











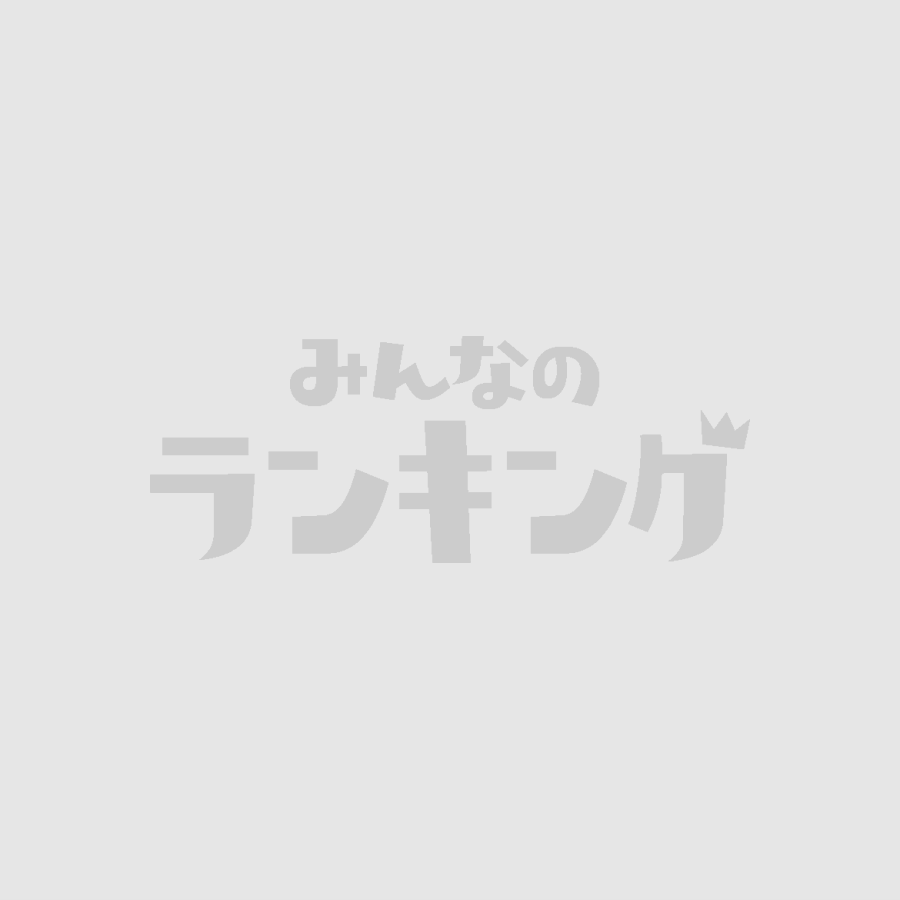
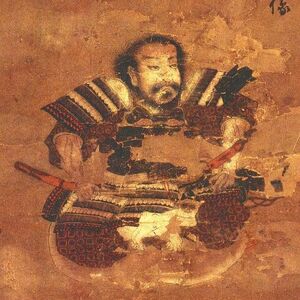



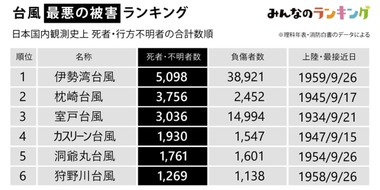



統率力、武勇、知略、政略全てにおいてトップレベル
桶狭間の戦いにおいて「小軍にして大敵を怖るることなかれ。運は天にあり。此の語は知らざるや。」という名言を残した
戦のプロフェッショナルを育てる、兵農分離を始めた
商業的大名
本拠地は清州→小牧→岐阜→安土
尾張を統一し、兄弟間の熾烈な抗争を勝ち抜いた織田信長は、1560年(永禄3年)、駿河の「今川義元」と対峙し「桶狭間の戦い」を迎えます。兵力では今川勢に分がある状況で、織田信長は出陣する前に家臣を鼓舞するための敦盛(あつもり)を舞いました。
敦盛は、「人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢幻のごとくなり。一度生を得て滅せぬ者のあるべきか」という一節で有名です。人生の短さを喩えた舞を終えた織田信長は、「法螺貝を吹け、武器をよこせ」と言い、出陣。
主君が家臣の目の前で披露したこの鼓舞は多くの若い家臣を勇気付け、兵力差の上で劣勢であった織田信長軍は、今川義元の首を討ち取りました。
今川義元を下した織田信長は、美濃を平定したあとに「足利義昭」(室町幕府15代将軍)を擁して天下を取ることを目指します。そして、この時期に織田信長は、天下人になることを宣言したという逸話が信長公記に記されていました。
ある時、丹波国桑田郡穴太村(現在の京都府亀岡市曽我部町穴太)の穴太城城主「赤沢義政」が織田信長に面会したとき、赤沢義政は織田信長にこう進言しました。「所有する鷹2羽のうち、いずれか1羽を信長様へ献上いたします」。すると織田信長は、「お気持ちは嬉しいが、いずれ私が天下を取るであろうから、それまで預けておく。大事に飼ってくれ」と返答しました。
織田信長が足利義昭を擁して上洛を開始したのは、1568年(永禄11年)のこと。そして、1575年(天正3年)に朝廷から「従三位権大納言兼右近衛大将」(じゅさんみごんだいなごんけんうこんえだいしょう)を任じられた織田信長は、事実上の「天下人」となりました。
鷹の寿命はおよそ11年。織田信長は宣言通りに、天下を取ったのです。
天下布武に向けていよいよ動き出した織田信長。1570年(元亀元年)に織田信長は、越前(現在の福井県)の「朝倉氏」征伐を開始しました。
京都から敦賀方面に侵攻し、越前中央部へ攻め込む予定でしたが、ここで近江の「浅井長政」が朝倉方に寝返ったという報告が入ります。浅井長政は、織田信長の妹「お市」(おいち)が輿入れした相手でした。
当初、浅井長政が寝返ったという報告を聞いても織田信長は信じませんでしたが、お市が織田信長に手紙を送ったことで、ようやく織田信長は、浅井長政の謀反が事実だと認めます。そして織田信長は、京都への撤退を余儀なくされました。幾多の戦を経て「朝倉義景」が足利義昭に和議を嘆願したことにより、両者の戦いは一時休戦することになったのです。
1571年(元亀2年)浅井・朝倉勢との休戦から1年後、織田信長は比叡山の「延暦寺」(現在の京都と滋賀の県境に位置する寺院)への攻撃を開始します。
比叡山に逃げ込んだ浅井・朝倉軍を匿ったのは、延暦寺の僧兵。以前から延暦寺の僧は、肉食や禁制であった女人を入山させるなど、京都の鎮守であるにもかかわらず仏門の道から外れ、勝手な振る舞いをしていました。
織田信長は熱心な仏教徒ではありませんでしたが、浅井・朝倉軍を匿ったことと併せて、延暦寺を敵とみなしたのです。
仏堂や神社を破壊・焼き尽くし、山下にいた老若男女の首を1人残らず刎ねていきます。比叡山には、数千もの死体がそこらじゅうに転がり、凄惨な光景が広がっていました。
浅井・朝倉軍を討伐した織田信長は、足利家と敵対する三好家と戦っていましたが、大坂本願寺が突如挙兵し、各地で一向一揆が勃発します。
織田信長は、本願寺と一向一揆の平定に追われることに。1574年(天正2年)には、伊勢長島(現在の三重県桑名市)で起こった「長島一向一揆」を鎮圧。この時、一揆勢は拠点に立てこもり、織田信長に助命を請いますが、織田信長はこれを拒否。「悪人たちは兵糧攻めにして、これまでの罪や悪行に対する鬱憤を晴らす」と述べ、風雨に紛れて逃げ出そうとした男女1,000人を捕らえて斬り殺します。
こうして織田信長は、各地の一揆を平定し、11年の歳月をかけて大坂本願寺を降伏させました。
延暦寺の焼き討ちや、一向一揆での織田信長の所業から、僧兵や一揆衆は織田信長のことを「第六天魔王」と呼ぶようになります。第六天魔王とは、仏道修行においての敵、すなわち「天魔」(てんま:人心を惑わす悪魔)のこと。僧兵や歯向かってきた人びとを容赦なく焼き討ちした織田信長の残虐さは、仏教徒にとってまさに天魔だったと言えます。
一方で、第六天魔王という呼び名に対して織田信長はまんざらでもなかったようです。延暦寺は、焼き討ちを受けたあと、仏門に入っていた「武田信玄」に庇護を求めており、武田信玄は非難の意をこめて織田信長に手紙を送っています。
この手紙では、武田信玄は自らを「天台座主沙門」(てんだいざすしゃもん:当時の日本仏教で最も強い権力を持っていた天台宗の代表)としたためており、これに対抗意識を燃やした織田信長は、手紙を返す際に「第六天の魔王信長」と記載したのです。
仏教の代表を自称した武田信玄に対して、仏教の敵を自称した織田信長。これ以上にない皮肉の効いた返しは、織田信長の度胸が据わった性格ぶりを示す逸話となっています。
1575年(天正3年)、織田信長は「長篠の戦い」で武田軍を相手に、戦場において日本史上初めて火縄銃を導入。結果は、織田信長の圧勝。武田軍を圧倒的な力で打ち倒した織田信長はその後、朝廷から「権大納言」、「右近衛大将」の官位を賜り、事実上の天下人となります。翌年の1576年(天正4年)には、琵琶湖の傍に「安土城」の築城を開始。そして、織田信長にとって幾度目かの試練がこの年から始まりました。
「第三次信長包囲網」と言われる、全国各地の大名らによる織田信長への侵攻が開始。京都を追放された足利将軍や、本願寺の僧兵をはじめ、越後国の上杉軍、中国地方の毛利軍、さらに家臣であった丹波国「波多野秀治」、但馬国「山名祐豊」(やまなすけとよ)らが相次いで反旗を翻します。
織田信長は、自身の家臣らを各地へ派遣し、次々と鎮圧。1570年(元亀元年)に浅井・朝倉軍による「第一次信長包囲網」から端を発した10年にも亘る「反信長連合軍」との戦いは、織田信長の重臣による裏切りと共に終焉を迎えます。
1582年(天正10年)6月、安土城から上洛した織田信長は「法華宗本門流」(ほっけしゅうほんもんりゅう)の大本山「本能寺」で、重臣「明智光秀」に襲撃されました。火が放たれた寺院の中で織田信長は自害。享年49歳。