1分でわかる「司馬遼太郎」
時代小説の大家「司馬遼太郎」
1923年生まれ大阪府出身の「司馬遼太郎」。1960年、前年に発表した『梟の城』で直木賞を受賞します。『梟の城』をきっかけにそれまで勤めていた新聞社を退社し、作家1本に絞りました。『梟の城』以降は、幕末を舞台にした代表作でドラマ化もされた『竜馬がゆく』や2018年に映画化された『峠』をはじめとして『燃えよ剣』、『国盗り物語』、『坂の上の雲』などの名作を次々と発表。ちなみに作品中の名言に、影響を受ける人も数多くいます。時代小説が評価される一方で『街道をゆく』や『この国のかたち』をはじめとする多数のエッセイを執筆。エッセイの中には『二十一世紀に生きる君たちへ』という子供へ向けた作品もありました。
書物を読みふけった司馬遼太郎
司馬遼太郎は少年時代、阿倍野のデパートで吉川英治の宮本武蔵全集を立ち読みで読破しました。いつも立ち読みだけで購入しないため、怒った売り場の主任が「うちは図書館やあらへん!」と言うと、「そのうちここらの本をぎょうさん買うたりますから……」と返したそう。






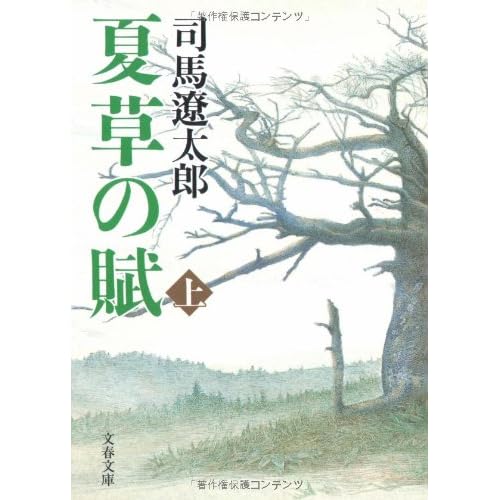


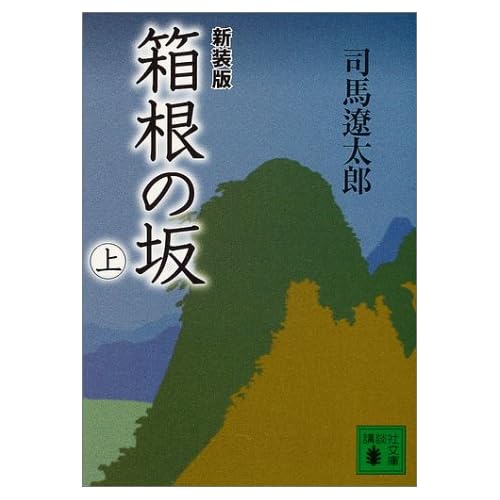




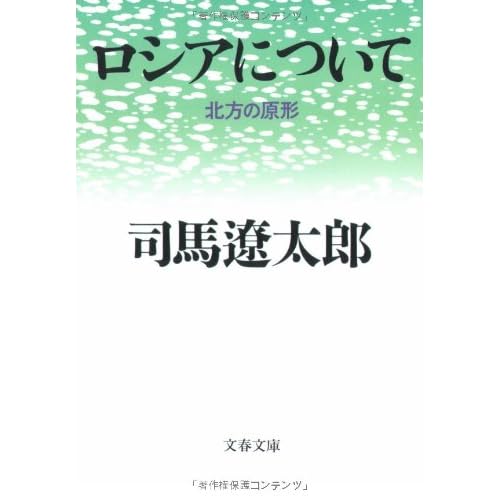








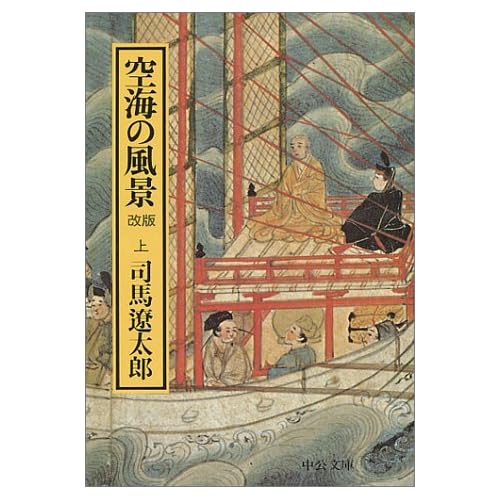
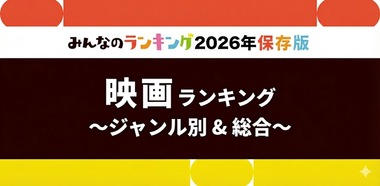
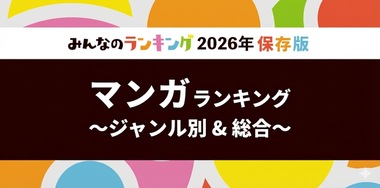











土方歳三の狂気
現代における新選組のイメージは司馬遼太郎の影響が非常に大きいと言われますが、特にここで描かれる土方歳三の人物像は鮮烈。
終盤にはもはや何が目的なのかという気すらしてくる土方の狂気。しかしその最期は、そうやって生きることこそが目的だったのかとも思えます。
はいとーんさん
1位(100点)の評価
幕末を違うアングルから楽しめる
私の中では「竜馬がゆく」と抱き合わせで読みたい作品。同じ時代を描いたものであるが、立場が違う。新選組(幕府側)の目線でストーリーが展開するので、より一層、幕末という動乱期への理解が深まる。その狂気ともいえる時代を生きた土方歳三の生き様が面白い。
チャッピーさん
5位(75点)の評価
全く興味の無かった新撰組に魅入らせた作品なので。
新撰組は、下克上を夢見る野心家の集まりでエピソードも立ち回りも泥臭く野蛮で、幕府の傭兵軍団のようなもの。勝てば官軍とはよく言ったもので、子供の頃から変わらない印象でしたが、この作品を読んで隊員の人間らしさに、違う側面もあったろう、と気付けました。
asuさん
2位(95点)の評価