ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位豚骨ラーメン
1位納豆
1位醤油ラーメン
1位お茶漬け
1位赤飯
1位桜餅
1位豚骨醤油ラーメン

中華そば(豚骨醤油ラーメン) by Ryosuke Hosoi / CC BY
2位鰹のたたき
2位味噌ラーメン
3位寿司
4位お好み焼き
4位すき焼き
5位とんかつ
6位親子丼
6位おでん
6位カツ丼
6位ちらし寿司
6位だし巻き
6位かき揚げ
6位おせち
7位ちくわ
7位天丼
7位茶碗蒸し
8位焼きそば
8位きんぴらごぼう
8位肉じゃが
8位豚汁
8位天ぷら
8位ひじき
8位切り干し大根
8位筑前煮
8位おから
ライフスタイルの新着記事
おすすめのランキング




あわせて読みたいランキング





















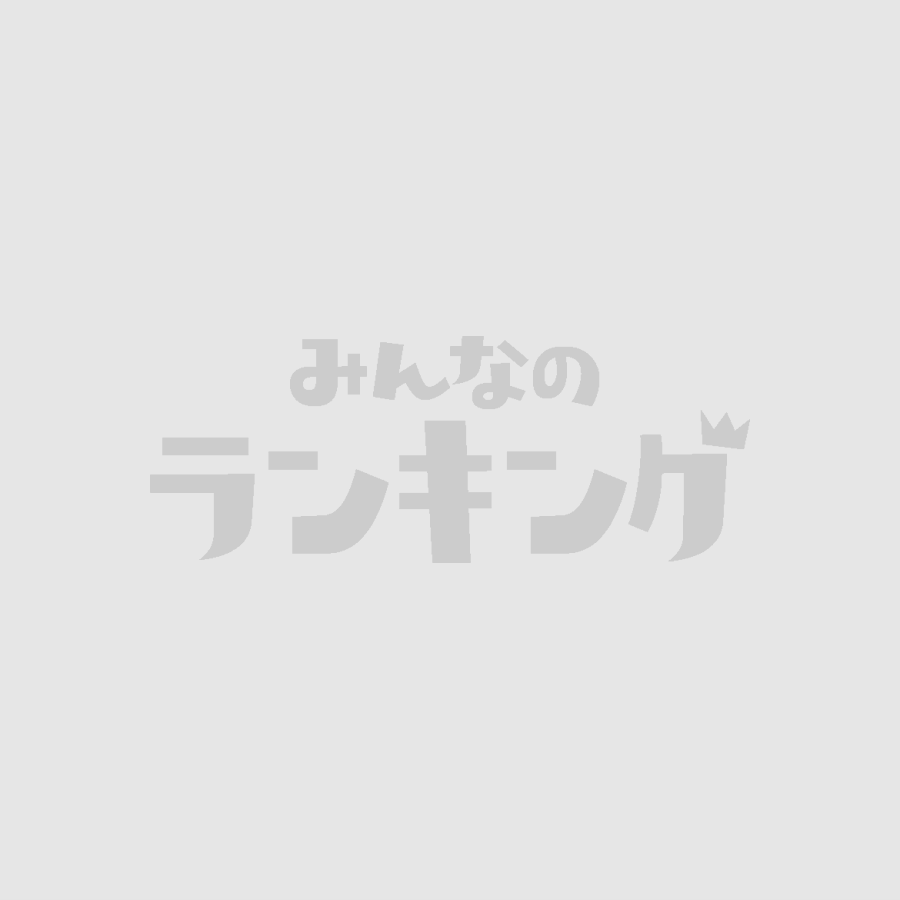

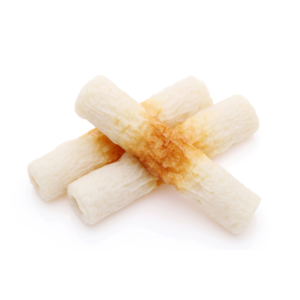












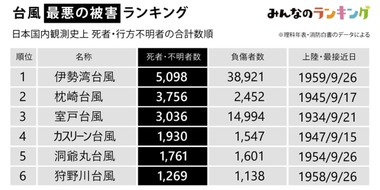



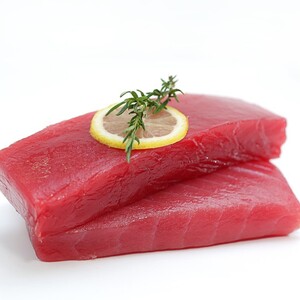
臭い(くさい)!!!!
匂いが駄目 反吐が出そう!!味醂と砂糖と醤油で味付けしたような料理が苦手!!「肉じゃがが大嫌いだ!!!!」と、表明したかったwww。彼女に作ってもらいたい料理人気No.1みたいな事をTVや雑誌で何度か目にした事があるが「ウソだろ!?!?」と思っている。